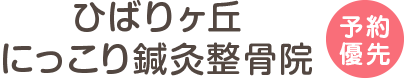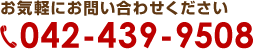体の芯が冷える…その原因と対策|自律神経・内臓冷えへの正しいアプローチ
2025年06月05日

体の芯が冷えると感じたら、自律神経や内臓の働きが乱れているサインかもしれません。にっこり鍼灸整骨院が、東洋医学的な視点を交えつつ、根本原因の見極め方や独自の施術・セルフケア方法を詳しく解説します。

体の芯が冷えるとは?よくある症状と冷えのタイプ
「最近なんだか体の奥から冷える感じがするんですよね…」
こんなご相談、当院でもよく耳にします。手足はそれほど冷たくないのに、なんだか体の中心がずっとひんやりしているような感覚。実はそれ、「体の芯が冷えている」状態かもしれません。
体の芯が冷えるって、どんな状態?
一般的に「冷え性」といえば、手先や足先が冷たくなるイメージがありますが、「体の芯が冷える」場合は少し事情が違います。お腹や腰、背中など、体の中心に近い部分が冷たく感じることが多く、内臓の働きにも影響している可能性があると言われています。
このような冷えは、ただの寒さだけが原因ではなく、自律神経の乱れや筋肉のこわばり、血流の滞り、そしてストレスなどが複雑に絡み合って起こることがあると考えられています。
女性に多い?見過ごされがちな芯の冷え
とくに女性はホルモンバランスの影響を受けやすいため、体の芯が冷えるタイプの冷え性になりやすいといわれています。生理不順や胃腸の不調、慢性的な疲労感などと併発しているケースも少なくありません。
「冷えている自覚はないけど、なんとなくだるい」「温めてもすぐ寒くなる」――そう感じる方は、実は体の“深部体温”が下がっているサインかもしれません。
にっこり鍼灸整骨院の見解と視点
にっこり鍼灸整骨院では、この「体の芯が冷える」という状態を、単に気温や生活環境のせいとは捉えません。
腹部の触診や皮膚温、舌の色・質、姿勢の崩れなどを丁寧に確認し、冷えの原因を多角的に見極める検査を行います。
また、骨盤のゆがみやインナーマッスルの低下、自律神経の緊張状態が巡りの悪さに繋がっていることもあるため、EMSによる深層筋トレーニングや、鍼灸による内臓機能の調整、温灸・ツボ刺激などを組み合わせた施術を提案しています。
体の表面だけでなく、「中」から温めることが、本当の意味での冷え対策につながると考えています。
#体の芯の冷え
#自律神経の乱れ
#内臓型冷え性
#東洋医学の視点
#にっこり鍼灸整骨院

主な原因|なぜ体の芯が冷えるのか?
「なんでこんなに体の芯が冷えてる感じがするんだろう…」
日常でふと感じるこの疑問。じつは、いくつかの要因が重なっているケースが多いんです。
自律神経の乱れが巡りを妨げている?
まず最初に考えられるのが、自律神経のバランスの乱れです。交感神経が優位になりすぎると、血管が収縮し、体の中心まで温かい血液が届きにくくなるといわれています。
特にストレスの多い生活や睡眠不足、不規則な生活習慣などは、自律神経の働きに影響を与えるとされており、それが「冷え」につながる場合があるのです。
当院では、腹部の緊張や舌の状態、脈の強さなどから、自律神経の傾向を丁寧にチェックしています。
筋肉の硬さと骨盤のゆがみも関係あり?
実は、筋肉の緊張や姿勢の崩れも、体の芯が冷える一因と考えられています。特に骨盤周囲の筋肉が固くなっていると、内臓の位置が微妙にずれ、血流やリンパの流れが滞りやすくなるといわれています。
また、姿勢が悪くなることで、肺や胃腸の動きも制限され、体温調整がうまくいかなくなることも。
にっこり鍼灸整骨院では、骨盤のバランスや肩甲骨まわりの柔軟性を検査し、姿勢からくる冷えにもアプローチします。
内臓の働きが低下している可能性も
「お腹が張りやすい」「便通が乱れがち」「食後に疲れる」
こんな症状がある方は、内臓の働きがやや弱まっているサインかもしれません。特に胃腸や腎臓、子宮まわりの血流が悪くなると、体の中心から冷える感覚を持つ方が増えるといわれています。
当院では、鍼灸や温灸を用いて「関元」「中脘」などのツボをやさしく刺激し、内臓機能を穏やかに整える施術を提案しています。無理に温めるのではなく、体の内側から少しずつポカポカ感を取り戻すことを目指しています。
当院ならではの「冷え」への多角的アプローチ
にっこり鍼灸整骨院では、冷えを「単なる寒さのせい」とは考えていません。姿勢・筋緊張・神経・内臓など、複数の視点から原因を分析し、患者さまごとに施術を組み立てていきます。
たとえば、深層筋のトレーニングにはEMSを活用し、ベッドに寝たままインナーマッスルを刺激して基礎代謝を引き上げるよう働きかけています。
さらに、日常のセルフケアも大切な要素のひとつ。食事の内容や入浴法、リラックスできる呼吸法なども、施術の一環としてお伝えしています。
#自律神経と冷え
#骨盤のゆがみ対策
#内臓の血流低下
#にっこり式温活
#冷えの原因を見極める

当院の検査法|体の冷えをどう見極めるのか?
「手足はあたたかいのに、なんか体の奥だけ冷たい気がするんです」
そう話される方が、実は少なくありません。ただ、体の芯の冷えは外からはわかりづらいため、適切に見極めるには“観察力”と“触れる力”が必要だと考えています。
見た目だけでは判断できない“冷え”
パッと見では元気そうに見えても、お腹を触ってみると冷たかったり、脈を診ると弱々しかったりすることがあります。そういったサインを丁寧に拾い上げていくのが、にっこり鍼灸整骨院の基本姿勢です。
まず、問診では「最近寝つきが悪くないか」「便通に変化はないか」「手足以外の冷えを感じることはあるか」など、日常生活に関することまで丁寧にお聞きします。そのうえで、実際に体に触れながら、冷えの原因や傾向を探っていきます。
東洋医学と現代的な視点を融合した検査
当院では、東洋医学に基づいた診察法を大切にしています。たとえば…
-
舌の色や形、苔のつき方を観察する「舌診」
-
脈の速さや深さ、リズムを確認する「脈診」
-
お腹の温度や硬さ、張り感をチェックする「腹診」
といった伝統的な検査方法をベースにしています。ただし、それだけではありません。
骨盤のゆがみや筋肉の左右差、姿勢のクセなど、構造的な部分にも注目して分析を行います。
「なんとなく冷える」という曖昧な感覚も、いくつかの検査を組み合わせることで、実際の体の状態と結びつけて整理できると考えています。
にっこり鍼灸整骨院だからこその視点
冷えの検査で特に意識しているのは、「自律神経のバランス」と「深部体温の低下傾向」です。
腹部や骨盤まわりを触ったときの温度差や、肌の色味、さらには呼吸の深さなど、さまざまな要素からその人の“体質”や“緊張度”を見極めていきます。
さらに、当院ではEMSを活用した検査も行っています。これは、深層筋がうまく働いているかをチェックし、代謝機能が低下していないかを確認する目的があります。冷えの原因が筋肉の働きにある場合、この検査が非常に役立つといわれています。
冷えはただの不快感ではなく、体の内部からのサインとも受け取れるもの。だからこそ、見落とさずに丁寧に向き合うことが重要だと考えています。
#冷えの検査
#東洋医学の見極め
#自律神経チェック
#舌診と脈診
#にっこり整骨院の冷え対策

にっこり式施術|体の芯から温まるアプローチ
「カイロを貼ってもお風呂に入っても、どうも温まりきらない…」
そんな“芯の冷え”に対して、外側から温めるだけでは限界があるといわれています。にっこり鍼灸整骨院では、内側からじんわり温まる“にっこり式”の施術アプローチで、冷え体質に寄り添っています。
東洋医学の知恵を活かしたあたため術
当院ではまず、東洋医学の基本でもある「気・血・水」の巡りを重視します。冷えのタイプが「気の不足」なのか、「血の滞り」なのかによって、施術の方向性が変わってくるためです。
特に冷えに効果的とされるのが、鍼灸です。
お腹周りの「関元」や足の「三陰交」などのツボを刺激することで、内臓の働きや血流を穏やかに整え、芯から温まってくる感覚が得られるといわれています。さらに、当院では温灸やホットパックを併用することで、無理なく深部まで熱が届くようなケアを心がけています。
インナーマッスルへの刺激で代謝もアップ
実は、冷えの原因が「筋力の低下」や「姿勢の崩れ」によって引き起こされることもあります。特に、深層のインナーマッスルが弱くなると、体温の保持がしづらくなる傾向があると言われています。
そこでにっこり鍼灸整骨院では、**EMS(電気刺激装置)**を用いたインナーマッスルへのアプローチも行っています。ベッドに横になったまま深層筋を鍛えることで、基礎代謝の向上を目指します。運動が苦手な方や、体力に不安がある方にもおすすめされている方法です。
姿勢調整×筋膜リリースで巡りを取り戻す
「冷えやすい人ほど姿勢が崩れていることが多い」——そういわれているのは、姿勢のゆがみが血流や内臓の圧迫を引き起こす可能性があるからです。
当院では、骨盤や背骨のバランスを整える施術と、筋膜リリースによる緊張緩和を組み合わせて実施しています。これにより、体内の巡りがスムーズになりやすく、冷えの改善につながることが期待されているのです。
「なんとなく冷える」その感覚に、丁寧に耳を傾けてあげることが、根本からの冷え対策の第一歩。にっこり式の施術で、内側からポカポカを目指してみませんか?
#にっこり式冷え対策
#東洋医学の冷えアプローチ
#鍼灸で芯から温まる
#EMSで代謝アップ
#姿勢と筋膜の調整で巡り改善

今日からできる!体の芯の冷えを防ぐセルフケア
「いつもお腹の奥が冷たい気がする…」
「足先は温かいのに、なんとなく全身がスッキリしない…」
そんな“芯からの冷え”を感じたとき、ちょっとした生活習慣の見直しが役立つことがあるといわれています。ここでは、当院がおすすめする“体の芯を温めるセルフケア”をご紹介します。
食べ物で体の中からポカポカに
まずは、食生活の見直しから始めてみましょう。冷えを防ぐためには、体を温める食材を意識的に摂ることがポイントです。
たとえば、しょうが・にんじん・ネギ・根菜類などは、東洋医学でも「陽性食品」とされており、体の深部を温める力があると言われています。一方で、冷たい飲み物や生野菜、甘いお菓子などは体を冷やしやすいため、摂り方に注意が必要です。
「朝ごはんにあたたかいスープを飲む」「おやつは常温以上のものに変える」といった小さな工夫からでも、冷えに対する体質改善が期待できるそうです。
呼吸とストレッチで内側から整える
実は、呼吸にも冷え対策のヒントが隠れています。浅く速い呼吸が続くと、交感神経が優位になり、血流が悪くなりがちです。
そこでおすすめしたいのが、腹式呼吸。5秒かけて鼻から吸い、お腹を膨らませて、口からゆっくりと吐き出す——これを1日5分行うだけでも、自律神経のバランスが整いやすくなるといわれています。
さらに、腰やお腹、股関節まわりのストレッチも取り入れてみましょう。当院では、腸腰筋や内転筋をゆるめるエクササイズをセルフケアとして提案しています。これらの筋肉がゆるむことで、骨盤内の血流がスムーズになり、結果として内臓の冷え対策にもつながると考えられています。
お風呂と服装の工夫も忘れずに
「冷えてるな」と感じた日は、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かってみてください。みぞおちまでしっかりお湯に浸かることで、副交感神経が優位になり、体がじんわりと温まってくる感覚が得られることもあるようです。
また、首・手首・足首の“3つの首”を冷やさないように意識した服装も効果的です。おしゃれも大事ですが、「今日は冷えそうだな」という日は、機能性インナーやレッグウォーマーを活用してみるのもおすすめです。
#冷え対策セルフケア
#腹式呼吸で温活
#食事で温める習慣
#にっこり式ストレッチ
#ぬるま湯入浴法
#西東京市#ひばりヶ丘#東久留米市#新座市