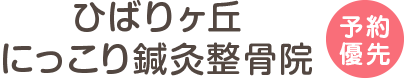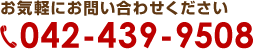坐骨結節 痛み 原因|長時間の座位や運動による影響と対処法
2025年05月20日

坐骨結節 痛み 原因について解説。長時間の座位や運動による影響で生じる坐骨結節の痛みの原因と、その対処法を詳しく紹介します。
坐骨結節とは?その役割と位置
坐骨結節の基本的な位置と構造
「坐骨結節(ざこつけっせつ)って、どこにあるか知ってますか?」
患者さんからこう聞かれることがよくあります。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は私たちが毎日のように使っている体の一部なんです。
坐骨結節とは、骨盤の下の方、ちょうどお尻の奥に位置するゴリッとした骨の突起部分を指します。座ったときに椅子に当たる“座骨”のあたり、まさにあの部分です。この坐骨結節には、太ももの裏にある筋肉「ハムストリングス」がくっついており、歩く・立つ・走るといった基本的な動きにも深く関係しています。
「座る」と「動く」を支える縁の下の力持ち
「たしかに座るとお尻の骨が当たる感じ、ありますよね」
その通りなんです。坐骨結節は、私たちが座るときに体重を受け止めてくれている重要な部分。そのため、長時間座っているとここに圧が集中し、痛みや違和感が出ることがあるんですね。
また、ハムストリングスはこの坐骨結節から始まって太ももの裏を通り、膝の裏あたりにまで伸びています。この筋肉が緊張したり、柔軟性を失ったりすると、筋肉の引っ張りによって坐骨結節に負担がかかりやすくなると言われています。
つまり、筋肉と骨の“つなぎ目”にある坐骨結節は、姿勢や体の使い方のクセにも敏感に反応してしまう場所なんですね。
当院でのアプローチ
ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院では、坐骨結節周辺の痛みについて、筋肉・骨格・神経のバランスを総合的に見ていきます。まず、筋膜の硬さや神経の癒着を評価する独自の検査を実施。必要に応じて鍼灸を使い、緊張をゆるめていくとともに、EMSによる筋力トレーニングで再発予防にもつなげていきます。
さらに、体幹や骨盤の安定性も痛みに影響していることが多いため、患者さん一人ひとりに合ったセルフケアも丁寧に指導しています。ストレッチや姿勢の見直し、普段の座り方など、日常生活の中でもケアできる方法を一緒に探していきましょう。
坐骨結節の痛みの主な原因
よくある原因は「使いすぎ」と「座りすぎ」
「なんかお尻の奥がズーンと痛い…でも何が原因かわからない」
そんなお悩みを抱えて来院される方、実はけっこう多いんです。
坐骨結節の痛みの原因としてよく知られているのが、「ハムストリングスの使いすぎ」と「長時間の座位姿勢」。特にスポーツをしている方や、デスクワークが中心の生活を送っている方に多く見られる傾向があるようです。たとえば、マラソンやサッカーなどで太ももの裏をよく使う人は、ハムストリングスが硬くなりやすく、それが坐骨結節を引っ張って炎症につながる可能性があると言われています。
また、「最近、在宅勤務が増えて一日中座ってるんですよね…」という声もよく耳にします。実際、硬い椅子に長時間座り続けると、坐骨結節に圧がかかりやすく、痛みが出やすくなるとも言われています。
坐骨神経との関係も見逃せない
さらに、見落とされがちなのが「坐骨神経の影響」。
「え、神経も関係あるの?」と驚かれることが多いのですが、坐骨結節の近くには坐骨神経が走っていて、筋肉や組織との間で癒着が起きると痛みやしびれの原因になることがあるんです。
当院では、このような場合、ただ筋肉の硬さを見るだけでなく、神経の通り道や癒着の有無まで丁寧にチェックしています。鍼灸や手技による施術で筋膜の癒着をゆるめながら、EMSで筋力低下を予防・改善するという多角的なアプローチを行っています。
また、痛みが出やすい動きや姿勢を把握し、それに合わせたセルフケア指導も徹底。たとえば、長時間座る方にはクッションの使い方や座り方の改善ポイントをお伝えしています。日常のちょっとした習慣の見直しが、再発防止に大きく関わると考えています。
症状と診断方法
「ただの腰痛?」と思って見逃しがちなサインとは?
「最近、長く座っているとお尻の奥がジワジワ痛いんです…」
そんな風におっしゃる方、けっこういらっしゃいます。
坐骨結節の痛みは、最初はただの“お尻の違和感”や“座りにくさ”として現れることが多いようです。「椅子に座ると片側だけが痛む」とか「床に座るとお尻の骨がズーンと重い感じがする」など、症状の出方は人それぞれ。ただ、いずれも“じわじわ系”の鈍い痛みからスタートするケースが多く、気づかぬうちに慢性化してしまうこともあると言われています。
また、ハムストリングスの起始部が炎症を起こしている場合には、座っている時だけでなく立ち上がる瞬間や歩き始めの一歩でも「ピキッ」とした鋭い痛みが出ることもあります。中には、坐骨神経への影響で太ももやふくらはぎまで痛みやしびれが広がるケースもあるようです。
当院での触診・評価方法とその理由
では、こうした痛みをどうやって判断していくのか?
ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院では、まずはしっかりとしたヒアリングから始めています。「いつから痛いのか?」「どの動きで痛みが出るのか?」「日常生活で困っていることは何か?」など、細かくお話を伺うことで、原因のヒントを探っていきます。
その上で、触診を通して実際に痛みの出る部位を確認。
坐骨結節まわりの圧痛(押したときの痛み)や、ハムストリングスの緊張状態、骨盤や股関節の可動域などもチェックします。さらに、必要に応じて整形外科的テストや神経の走行確認なども行い、総合的に評価していきます。
当院では、画像診断は医療機関と連携しつつ、徒手による評価を中心に、筋膜や神経の癒着といった機能的な問題にも着目しています。鍼灸やEMSを併用しながら、単なる炎症へのアプローチではなく、体のバランスや使い方のクセまで視野に入れて施術を組み立てていきます。
当院の症状に対する考え方と施術方法
「そこだけ揉んでも改善しない」──根本を見抜く視点
「お尻が痛いんですけど、そこをほぐせば良くなりますか?」
患者さまからこう尋ねられることがよくあります。でも、実際には“痛い場所=原因の場所”とは限らないんですよね。
ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院では、坐骨結節の痛みに対して、局所的な対応ではなく“全体のつながり”を大切に考えています。たとえば、筋肉の使い方のクセや姿勢のバランスが乱れていると、痛みの原因が坐骨結節に集中してしまうことがあると言われています。
そこで当院では、まず「どこが痛いか」よりも、「なぜそこに負担がかかっているのか」を探るための評価を行います。
筋膜の癒着や神経の滑走障害、さらには骨盤の歪みや体幹の不安定性まで含めてチェックしていくことが大切だと考えています。
一人ひとりの状態に合わせた施術プラン
「えっ、そんなところまで見るんですか?」と驚かれることもありますが、私たちにとっては当たり前のステップです。
当院の施術は、次の3つのアプローチを組み合わせています。
-
鍼灸施術で深層筋や神経の緊張をゆるめる
特に坐骨神経に圧がかかっているケースでは、筋肉や神経の過敏な反応がみられるため、ツボや経絡を用いたアプローチが有効だと言われています。 -
手技療法で筋膜や骨格のバランスを調整
触診を通じて確認した癒着部位や硬結に対し、当院独自の手技を行い、体の動きそのものを整えていきます。 -
EMSで運動が苦手な方にも無理なくトレーニング
特に骨盤周囲の安定性が不足している場合は、インナーマッスルを鍛えることが再発予防につながると考えられており、EMSによる寝たままの筋トレもご提案しています。
施術だけで終わりではなく、普段の座り方や歩き方のクセまで見直し、セルフケアとして行えるストレッチや姿勢指導もセットでお伝えしています。
「施術後に楽になったけど、また痛みが戻るんです」と感じたことがある方ほど、当院のような“根本に目を向ける施術”が合っているかもしれません。
予防と再発防止のために
生活習慣を見直すだけで、坐骨結節の負担は減らせる?
「また痛くなるのが不安で…何か気をつけることってありますか?」
施術後によくいただくご質問のひとつです。確かに痛みが落ち着いたとしても、普段の生活習慣がそのままだと、再発のリスクは高まるとも言われています。
まず見直したいのは、「座り方」と「座る時間」。
硬い椅子に長時間座ることが多い方は、坐骨結節に繰り返し圧がかかりやすくなります。ですので、1時間に1回は立ち上がってストレッチをする、骨盤が立つような座面を選ぶ、といった工夫が予防につながると考えられています。
また、姿勢もポイント。猫背や反り腰などの姿勢のクセがあると、体重のかかり方が偏ってしまい、お尻の奥にある筋肉が緊張しやすくなると言われています。日常の中で、「あ、今丸くなってたな」と気づける意識づけが大切ですね。
当院が提案するセルフケアと再発予防のポイント
ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院では、施術だけで終わらず、セルフケアの指導にも力を入れています。
たとえば、ハムストリングスの柔軟性を保つための簡単なストレッチや、骨盤まわりを安定させるための体幹トレーニングなど、その方の生活環境に合わせた方法を提案しています。「これなら家でも続けられそう!」と感じてもらえるように、無理のない内容を一緒に考えていくことを大切にしています。
さらに、EMSによるインナーマッスル強化も併用することで、運動が苦手な方や筋力が落ちてきた方でも、寝たまま安全にトレーニングができるようサポートしています。骨盤の安定性が高まると、坐骨結節への負担も分散されやすくなると言われています。
痛みが出る前の“ちょっとした違和感”の段階でケアを始めることが、再発を防ぐ一番の近道かもしれません。
「最近、座ってるとお尻が気になる…」そんな方は、ぜひ生活習慣の見直しから始めてみましょう。