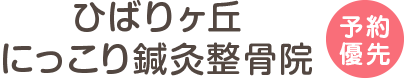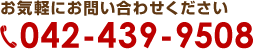扁平足 チェック|自宅で簡単にできるセルフ診断と当院の専門ケア
2025年06月02日

扁平足 チェックは自宅で簡単に行えます。本記事では、セルフチェック方法や扁平足の原因・症状、当院の専門的な施術やセルフケア方法をご紹介します。足の健康が気になる方はぜひご覧ください。

扁平足とは?その特徴と影響
扁平足ってどんな状態?
「土踏まずがなくなっている気がするんですけど…これって扁平足ですか?」
こんな声、実際によく聞きます。扁平足とは、足の内側にあるアーチ構造がつぶれ、足裏全体が床にベタッと接するような状態を指すと言われています。わかりやすく言えば、「土踏まずがなくなっている状態」とイメージしてもらえると良いかもしれません。
通常、土踏まずは体重のかかる衝撃を吸収する“バネ”のような役割を果たしていますが、扁平足になるとその機能が低下しやすくなるとされています。
扁平足による体への影響とは?
「ちょっと歩いただけで足が疲れる…」「膝や腰までだるくなるんです」——実はこれも、扁平足のサインかもしれません。
扁平足の人は、足裏のアーチがうまく衝撃を吸収できないため、歩行や立位時の負担が膝や股関節、さらには腰へと広がる可能性があると言われています。また、足指が使いづらくなり、つまずきやすくなるといったこともあるそうです。
さらに、お子さんの場合は成長過程でのバランスに影響を与える可能性もあるため、早期のチェックが大切とされています。
当院の考え方と施術アプローチ
当院「ひばりが丘にっこり鍼灸整骨院」では、扁平足による体への負担をトータルで考えています。単に足裏だけを見るのではなく、骨盤の傾きや姿勢のクセ、足首や股関節の可動域までを総合的にチェックし、全身のバランス調整を行います。
初回では、立位姿勢・足圧・足指の動きなどを細かく検査し、必要に応じてEMSや徒手による筋力調整、さらには足底の柔軟性改善を目的とした施術を取り入れています。
また、ご自宅でできる「タオルギャザー」や「足指グーパー体操」などの簡単なエクササイズ指導も行い、無理なく続けられるケアを重視しています。
「もしかして自分も…?」と思ったら、一度チェックしてみることをおすすめしています。放っておくより、少し早めに行動することで、日常の歩行がグッと快適になることもありますよ。
#扁平足とは
#足の疲れやすさ
#足裏アーチの役割
#整骨院でできること
#にっこり鍼灸整骨院の施術

自宅でできる扁平足のセルフチェック方法
簡単チェックで足の状態を知ろう
「もしかして、これって扁平足…?」と気になったとき、病院に行く前にまず自宅で簡単にチェックしてみたくなりますよね。そんなときにおすすめなのが、いくつかの“セルフチェック”方法です。自分の足の状態を把握することで、ケアへの第一歩になります。
まずご紹介したいのが「足跡チェック」です。やり方は簡単。濡らした足で紙の上に立ち、その足跡を観察するだけ。土踏まずの部分が紙にくっきり写っていたら、アーチが潰れている可能性があるとも言われています。一方で、土踏まずがきれいに抜けているなら、アーチがしっかりしている可能性が高いようです。
次に「ボールペンチェック」もあります。椅子に座り、足を床につけた状態で、土踏まずの下にボールペンを差し込んでみます。スッと通ればアーチがある程度保たれているサイン。逆に引っかかってしまうようなら、扁平足の傾向があるかもしれません。
足の動きにも注目してみよう
扁平足の方は、足指がうまく使えていないケースも多いです。「足指じゃんけん」や「タオルギャザー」などで足指の可動性や筋力をチェックするのも効果的だとされています。足の指でタオルをたぐり寄せるのが難しい場合、足底筋群がうまく使えていない可能性も考えられるでしょう。
当院では、来院された方に対し、このような足の動きや足指の機能も細かくチェックしています。姿勢や重心のバランス、骨盤や股関節との関係も含めて見ていくため、「単なる足の問題」と切り離さず、全体的に見ることが特徴です。
また、施術だけでなく、患者さま自身が日常生活で取り組める簡単なケア方法もお伝えしています。特別な道具がなくてもできる運動が中心なので、無理なく継続していただけますよ。
「もしかして…」と感じたときは、まず今日からチェックを始めてみませんか?自分の足と向き合うことで、今後の歩き方が変わるきっかけになるかもしれません。
#扁平足チェック
#セルフチェック方法
#足跡テスト
#足指エクササイズ
#整骨院の足の見方

扁平足の原因とリスク要因
どうして扁平足になるの?その背景を探ってみよう
「子どもの頃から土踏まずがなかった気がするんですけど…」「大人になってから、足が疲れやすくなったような…」
こんな声、実際に当院にもよく寄せられます。扁平足の原因は、ひとつに決めつけられるものではなく、いくつかの要因が重なり合っていることが多いと言われています。
まず、先天的な骨格の特徴が関係しているケース。いわゆる生まれつきアーチが低い方もいらっしゃるようです。一方で、大人になってから土踏まずが低下してくる「後天性扁平足」もあります。これは加齢や筋力低下、体重の増加、運動不足などが関与していると考えられています。
特に、長時間の立ち仕事をしていたり、クッション性の低い靴を履いていたりすると、足裏の筋肉や靭帯に余計な負担がかかりやすくなります。その負荷が積み重なることで、土踏まずがだんだん落ちてきてしまうというわけです。
放っておくとどうなる?リスクの広がりとは
「ただの足の形の問題でしょ?」と思ってしまいがちですが、扁平足が進行すると、足の疲れやすさや痛みだけでなく、膝・股関節・腰などへの負担も広がる可能性があると言われています。
アーチが崩れると足首の動きに影響が出てきて、結果として歩行や姿勢のバランスが崩れやすくなるからです。そのせいで、肩こりや腰のだるさにまでつながってくるケースも見受けられます。
当院では、こうした足のアーチの問題に対し、足首の柔軟性、股関節の動き、骨盤の傾きなども含めて全体を見ながら対応しています。立位での重心バランスや歩行分析も行い、根本的な体の使い方から整えていくことを大切にしています。
また、足裏の筋肉を鍛える簡単な運動や、正しい靴の選び方など、日常生活の中で取り入れられるセルフケアも一緒にご案内しています。
少しでも「気になるかも…」と思ったら、まずは足元から見直してみるのがおすすめです。体を支える基盤として、足はとても大切な存在なんです。
#扁平足の原因
#後天性扁平足
#足の筋力低下
#リスクと予防
#整骨院での全身チェック

当院の扁平足に対する施術と検査方法
扁平足を根本から見直すために
「足がだるいけど、扁平足って関係あるのかな?」「整骨院ってどこまで見てくれるんだろう?」
そんな疑問を抱えている方にこそ、当院の施術や検査方法について知っていただきたいと思っています。ひばりが丘にっこり鍼灸整骨院では、ただ土踏まずの形だけを見るのではなく、全身のバランスや生活習慣も含めたアプローチを大切にしています。
まず、初回来院時には足元の視診だけでなく、立位での重心バランス、足の柔軟性、足指の可動域などをしっかり確認。さらに必要に応じて骨盤や股関節の動き、背骨のS字カーブなどもチェックして、扁平足が他の部位に与えている影響までを丁寧に分析していきます。
当院独自の検査・施術アプローチ
「なんでこんなところまで見るんだろう?」と思うかもしれません。でも実は、扁平足は全身に波及する可能性があると言われているんです。
当院では、筋膜リリースや骨盤・足関節の調整、EMSによる足底筋群の活性化など、さまざまな手技と機器を組み合わせて施術を行っています。特に歩行時のクセや体重のかかり方に注目し、必要に応じてトレーニング指導も行っています。
さらに、自宅でできるセルフケアも重視しています。タオルギャザーやつま先立ち、足指のグーパー運動など、無理のない範囲で続けられる方法をご提案。継続的な改善を目指す上で、「毎日ちょっとだけやってみようかな」と思える内容をお伝えしています。
私たちは「土踏まずを戻すこと」をゴールにはしていません。その方の生活や体の状態に合わせた「負担の少ない歩き方」や「楽に動ける体」を作っていくことを目指しています。
どこに相談していいか迷ったら、一度当院にご相談ください。足元から体全体を見直すヒントが、きっと見つかるはずです。
#扁平足の整体アプローチ
#整骨院の検査内容
#足と全身のバランス
#筋膜リリースとEMS
#自宅でできる足ケア

扁平足の改善・予防のためのセルフケアと日常生活の工夫
続けやすい工夫がカギ!セルフケアで足を支えよう
「土踏まずがないと言われたけど、何をしたらいいか分からなくて…」
「仕事も忙しくて、通院だけじゃなかなか改善できそうにないんです」
こんなお悩みを抱えている方にこそ、自宅でできる簡単なセルフケアをおすすめしたいと思います。当院では、扁平足の改善や予防に向けて、日常に取り入れやすい工夫を大切にしています。
たとえば、「タオルギャザー」という運動。床に置いたタオルを足の指でたぐり寄せるシンプルな動きですが、足裏の筋肉を使う感覚が自然と身についていくと言われています。テレビを見ながらでもできるので、続けやすいのがポイントです。
また、つま先立ちでふくらはぎや足首を刺激したり、足指のグーパー運動を取り入れたりするだけでも、足の安定性に変化が見られる場合があります。
毎日の動作や靴選びにもヒントが
セルフケアと並んで大切なのが、「足に優しい生活習慣」。たとえば、長時間の立ち仕事をするときには、クッション性のある靴や、アーチサポート付きのインソールを使うだけでも負担が減ることがあるようです。
また、立ち方や歩き方を少し意識するだけでも、足への圧力が変わることがあります。重心が内側や外側に偏っていないか、足の指まで使えているか、気にしてみてくださいね。
当院では、こうした足の使い方や生活習慣の見直しまで含めてアドバイスしています。「できるだけ再発を防ぎたい」「仕事や家事で忙しくても、少しずつケアしていきたい」という方のために、無理のない方法をご提案しています。
足は、体を支える大切な土台です。毎日コツコツとケアを続けることが、将来の快適な歩行につながるかもしれません。
#扁平足セルフケア
#足裏トレーニング
#予防のための靴選び
#タオルギャザー運動
#整骨院での生活指導
#西東京市#ひばりヶ丘#東久留米市#新座市