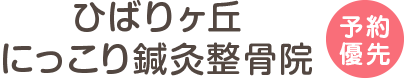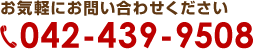発熱 腰が痛い 対処法|風邪やインフルエンザ時の腰痛の原因と効果的な対処法
2025年05月29日

発熱 腰が痛い 対処法をお探しの方へ。風邪やインフルエンザ時に腰痛が起こる原因と、その対処法について解説します。

発熱時に腰が痛くなる原因とは?
発熱と腰痛、その意外な関係とは?
「熱が出ると、なんだか腰までズーンと重くなるんですよね…」
こんな声、実はよく耳にします。発熱と腰の痛みは一見関係なさそうに感じるかもしれませんが、実はいくつかの理由が重なって腰痛が出ることがあると言われています。
筋肉の緊張が痛みにつながる
まず考えられるのが、発熱による筋肉のこわばりです。熱があると体がブルブル震えますよね?あの震え、「悪寒」と呼ばれる反応で、体温を上げようとする自然な防御反応なのですが、筋肉は無意識に緊張状態になります。その緊張が長引くと、腰まわりの筋肉が固まり、痛みを引き起こすことがあると考えられています。
特に中腰で過ごすことが多い方や、普段から腰に負担がかかりやすい方ほど、熱が出た時に腰痛が起きやすい傾向があるようです。
免疫反応による炎症も一因に
もう一つは、発熱=体内の炎症反応という視点。風邪やウイルス感染があると、体は免疫を総動員して対抗します。このとき「サイトカイン」と呼ばれる炎症性物質が分泌され、全身の関節や筋肉に違和感や痛みを感じることがあると言われています。
つまり、腰そのものに原因があるのではなく、体全体が“炎症状態”になっていることで腰の不調が表に出ているパターンもあるんですね。
横になりっぱなしで血流も低下しがち
また、体調が悪くなるとどうしてもベッドに横になって過ごす時間が増えます。動かないことで腰まわりの筋肉が硬くなり、血流も悪化。それが腰の重だるさや痛みに拍車をかけていることもあるようです。
実際に、ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院でも「熱が下がったあと、なぜか腰がつらいままなんです…」という方が多くいらっしゃいます。検査で確認してみると、腰部の筋膜や深部筋がガチガチに緊張しているケースが少なくありません。
当院では、まず体全体の状態を触診と可動域検査で確認し、必要に応じてEMSで筋肉の緊張緩和を図ったり、内臓疲労による姿勢のアンバランスを整えたりといったアプローチを行っています。
「ただの腰痛」だと思って放置せず、体からのサインをしっかり読み取ることが大切ですね。
#発熱と腰痛の関係
#筋肉の緊張による腰痛
#免疫反応と炎症
#自宅療養時の注意点
#ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院の考え方

自宅でできる対処法
腰の痛みと発熱を同時に感じたら?自宅でできる簡単ケア
「熱が出てるだけでもつらいのに、腰まで痛くて動けない…」
そんなふうに感じた経験はありませんか?発熱と腰痛が同時に起こると、日常の何気ない動作すら苦痛になりますよね。でも、いくつかの対処法を知っているだけで、症状が少しラクになることもあるんです。
ここでは、ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院がご紹介する、無理なくできる自宅ケアをお伝えします。
1. まずは腰を温めるところから
「腰が痛いなら冷やした方がいいですか?」と聞かれることも多いのですが、発熱時の腰痛の多くは筋肉の緊張や血流の滞りが関係していると考えられているため、温める方が向いていることが多いです。
湯たんぽや温熱パッド、あるいは蒸しタオルなどを腰に当てて、10〜15分ほどゆっくり温めてみてください。じんわりと温まる感覚が、重だるさや突っ張る感じをやわらげてくれるかもしれません。
2. 動ける範囲で「軽く動く」もアリ
「具合が悪いときは横になるのが一番」と思いがちですが、まったく動かない時間が長くなると、逆に筋肉が固まって腰痛が強くなることもあるようです。
無理のない範囲で、寝返りをうつ・軽く腰をひねる・仰向けで両膝を立ててゆっくり左右に倒す…など、呼吸を止めずにゆったり動かしてあげるのがポイントです。
もちろん、「しんどくてそれどころじゃない…」という場合は、ムリにやる必要はありません。少し体調が落ち着いてきたときにだけ、試してみてください。
3. 水分補給は「温かく」がカギ
発熱中は体の水分が失われやすいため、こまめな水分補給が必要です。ここで冷たい飲み物をがぶがぶ飲むと、内臓が冷えて腰の筋肉にも影響が出ることがあります。
おすすめは、白湯や常温のお茶。とくに内臓の働きが低下しているときには、温かい飲み物の方が体への負担が少なく、巡りがよくなるとも言われています。
4. にっこり鍼灸整骨院が提案する、寝ながらEMSケア
当院では、体調不良で運動ができない方のために、寝たままできるEMS(電気的筋肉刺激)による筋肉ケアも行っています。これは腰の筋肉をピンポイントで刺激し、血流促進や筋肉の緊張緩和を図る方法として注目されています。
ご来院が可能になった段階でのご相談はもちろん、電話やLINEでのセルフケアアドバイスも行っておりますので、無理せずご活用ください。
#発熱時のセルフケア
#腰痛の温熱療法
#寝たままストレッチ
#水分補給の工夫
#にっこり鍼灸整骨院のEMS対応

市販薬の活用
発熱と腰の痛みに使える市販薬は?
「熱もあるし腰も痛い…病院に行くほどじゃないけど、なんとかしたい」
そんなとき、手軽に使える市販薬はとても頼もしい存在です。ただし、正しく選んで使うことが大切。ここでは、発熱と腰痛の両方に対応できる市販薬の活用ポイントについてわかりやすくお伝えします。
解熱と痛み、どちらもケアできる薬とは?
市販薬でよく選ばれているのが、「アセトアミノフェン」や「イブプロフェン」といった解熱鎮痛成分が入ったお薬です。これらは、熱を下げるだけでなく、腰や関節の痛みにも作用すると言われています。
たとえば、「バファリン」「ノーシン」「タイレノールA」などは薬局で目にすることが多いですが、成分や効き方に違いがあるため、体質や症状に合わせて選ぶことが大切です。
「胃が弱いから、できればやさしいタイプがいいんだけど…」
そんな方にはアセトアミノフェン主体の製品が使いやすいかもしれません。胃への負担が比較的少ないとされています。
湿布や外用薬も選択肢に
熱が下がったあとも腰の痛みが残っているときには、「温感湿布」や「冷感湿布」を使うのも一つの手です。温湿布は血流を促し、筋肉のこわばりをやわらげる方向に働くとされ、冷湿布は炎症をしずめたり、熱感があるときに使われることが多いです。
ただ、「どちらが正解か」は個人差があるため、貼ってみて心地よく感じる方を選ぶのがポイントです。
市販薬だけに頼らず体の状態も見直してみる
にっこり鍼灸整骨院では、単に腰痛という表面的な症状だけでなく、自律神経の乱れや内臓疲労の影響、姿勢バランスの崩れまで広い視点でチェックしています。発熱中はとくに体全体が弱っているため、内臓と筋肉、そして自律神経のつながりにも着目したアプローチが重要だと考えています。
市販薬で一時的に症状が和らいでも、同じような不調が繰り返すようなら、根本的な原因にアプローチする必要があるかもしれません。そんなときは、当院の独自検査を受けてみるのも選択肢のひとつです。
#発熱と市販薬の選び方
#腰痛に使える薬とは
#解熱鎮痛剤のポイント
#湿布薬の種類と使い方
#にっこり鍼灸整骨院の根本施術

医療機関を受診すべき症状
発熱と腰痛、それって放っておいて大丈夫?
「熱があるだけでもしんどいのに、腰までズキズキするなんて…これって様子見でいいのかな?」
そう思ってしまう気持ち、よくわかります。ただし、中には早めに医療機関での確認が必要なケースもあると言われています。ここでは、どんなときに受診を検討すべきか、その目安についてお伝えしていきます。
こんな症状があるなら、注意が必要かも
まず、一番気をつけたいのが「高熱が続く」「腰の痛みがどんどん強くなる」「動けないほどのだるさを感じる」といった場合です。これらは単なる筋肉疲労ではなく、内臓の不調や感染症、あるいは泌尿器系のトラブルが隠れていることもあると言われています。
たとえば、腎盂腎炎や尿路感染症などの場合、腰の片側にズキッと鋭い痛みが出ることがあり、発熱とセットで現れることもあるそうです。こうしたケースでは市販薬やセルフケアだけでは対応しきれないことがあるため、早めの判断が求められます。
また、「足のしびれが出てきた」「感覚が鈍くなっている気がする」といった神経症状も見逃せないポイントです。これは、腰椎まわりの神経に関わる疾患が背景にあることもあるため、ひとまず専門機関での触診を受けておくと安心です。
いつもと違う“感覚”がヒントになることも
「なんとなくイヤな感じがする」「いつもと違うだるさがある」
このような“違和感”も、体からの大切なサインかもしれません。実際に、ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院に来られる方の中には、「熱が下がったあともずっと腰の違和感が抜けなくて…」と話される方も多いです。
当院では、そういった背景を踏まえて、腰だけを見るのではなく、自律神経の状態や内臓の負担、全身の姿勢バランスにも目を向けながら検査を進めています。症状の裏側にある“見えない不調”を明らかにするためには、単に痛みの場所だけに注目せず、全体からアプローチしていくことが大切だと考えています。
#発熱と腰痛の注意サイン
#医療機関を受けるべき症状
#尿路感染症との関係
#感覚異常の見逃し注意
#にっこり鍼灸整骨院の全身評価

予防と日常生活での注意点
発熱と腰の痛みを防ぐために、今日からできること
「またあの腰の痛みがくるかと思うと怖いんです…」
実際、発熱と腰痛がセットで起きた経験のある方からは、こうした声をよく聞きます。でも、ちょっとした生活の工夫を続けることで、再発リスクを減らす手がかりになるかもしれません。
ここでは、ひばりヶ丘にっこり鍼灸整骨院が考える、日常で意識したいポイントを紹介します。
1. 体を冷やさない意識をもつことが第一歩
「暑いからといって冷房ガンガン…それが実は腰痛の引き金になることもあるんです」
というのも、冷えは筋肉の緊張を招き、血流を悪くしてしまう要因と考えられているからです。とくに女性は内臓の冷えから腰の痛みに発展するケースもあると言われています。
夏でもお腹や腰を冷やさないよう腹巻きを活用したり、湯船につかる習慣をつけたりするのがおすすめです。
2. ストレッチと軽い運動で“流れ”を作る
長時間座りっぱなしや立ちっぱなしは、腰に負担をかけやすい姿勢です。
「気がつくとずっと同じ姿勢だった…」という日はありませんか?
そんなときは、背伸びや骨盤を回すような簡単なストレッチを入れてみましょう。たった1〜2分でも、筋膜や血流の“流れ”を良くすることが期待できるとされています。
当院では、EMSによるインナーマッスル強化とセットで、患者さま一人ひとりの体に合わせたセルフケア方法も提案しています。無理せず続けられる内容なので、気になる方はご相談ください。
3. 睡眠と食事の質が意外とカギ
「忙しくて寝るのが遅くなっちゃう」「朝ごはんはほぼ食べない」
このような生活が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、体調不良や腰痛のリスクも高まると言われています。
睡眠は最低6時間以上を意識し、朝食には温かい汁物や発酵食品を取り入れるのもおすすめ。腸内環境が整うことで、内臓疲労が軽減され、結果的に腰への負担も減る可能性があるようです。
#腰痛予防の生活習慣
#冷え対策と血流改善
#ストレッチと運動習慣
#睡眠と食事の見直し
#にっこり鍼灸整骨院の予防ケアアドバイス
#西東京市#ひばりヶ丘#東久留米市#新座市