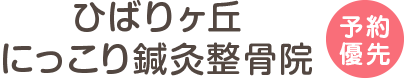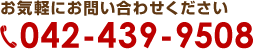背中の痛み だるさ 倦怠感:原因・セルフチェック・当院のアプローチ法を徹底解説
2025年06月17日

背中の痛み だるさ 倦怠感に悩む方へ。筋肉・姿勢・ストレス・内臓など原因を総整理し、当院独自の検査ポイント・施術方法・セルフケアまで一挙解説します。
背中の痛み・だるさ・倦怠感とは?症状の特徴と影響
症状の背景には、意外なサインが隠れているかも?
「最近、背中がずーんと重だるいんですよね…」
「特に何かした覚えはないのに、疲れが抜けないし背中も痛くて…」
そんなお悩みを抱えている方、意外と多いんです。
背中の痛み・だるさ・倦怠感というのは、単なる筋肉の疲労だけでなく、姿勢のクセや内臓からのサイン、自律神経の乱れまで関係していることがあると言われています。特に、デスクワークやスマホの使用が増えている現代では、前かがみの姿勢が続くことが多く、肩甲骨まわりや背骨周辺の筋肉に負担がかかりやすい状況です。
このような慢性的な違和感は、無理な姿勢の積み重ねからくる「筋膜の癒着」や「関節の可動性低下」が原因となるケースが多いと当院では考えています。検査では、骨盤の傾きや肩甲骨の可動域、呼吸時の肋骨の動きなどをチェックし、どこに“動きの制限”があるかを丁寧に見極めます。
また、痛みの出方が鈍く、じわじわと続く場合、自律神経の影響も疑われるとされています。睡眠の質が落ちていたり、常に交感神経が優位な生活スタイルになっていたりすると、体が休まらず、慢性的な疲労感として背中にサインが出てくることもあるようです。
「病院では異常なしと言われたけど、なんとなく調子が悪い…」そんなときは、当院のような整骨院で“体の使い方”や“筋・骨格のバランス”を専門的に見てもらうことがひとつのヒントになります。
さらに、内臓疾患(腎臓、膵臓、胃など)や婦人科系の不調が背部に関連痛として現れることもあるため、左右どちらかに偏った痛みがある、発熱や吐き気を伴うなどの症状があれば、早めの医療機関の相談も大切です。
一時的なものだと放っておかず、「その違和感、体がくれた大事なメッセージかもしれない」と捉える視点が、健康への第一歩になるかもしれません。

原因別セルフチェックポイント
痛みの種類と場所からセルフチェックしてみよう
「背中が痛いけど、病院に行くほどじゃない気もするし…何が原因なんだろう?」
そんなふうに感じている方、実は多いのではないでしょうか。背中の痛み・だるさ・倦怠感といっても、原因はひとつではありません。まずはご自宅でできるセルフチェックから始めてみましょう。
例えば、「ズキズキするような鋭い痛み」が特定の動作で強くなる場合、筋肉や関節の炎症が関係していると言われています。特に肩甲骨まわりや背骨の際に集中して痛む場合、姿勢不良や同じ動作の繰り返しによって筋肉が過剰に緊張していることもあるようです。
一方、「だる重い感じ」や「じんわりとした違和感」が続く場合は、自律神経の乱れや内臓からの関連痛の可能性も考えられます。たとえば、食後や睡眠不足のときに悪化するようであれば、胃腸や肝臓などの機能の低下と関係していることがあるとも言われています。
他にも、「片側だけに出る痛み」や「痛みと一緒に手足のしびれがある」場合、神経由来の可能性も。特に首〜背中のラインで圧迫が起きていると、手の方にしびれが広がることがあるため注意が必要です。
当院では、単に「どこが痛いか」だけではなく、「どんなときに」「どんなふうに痛むか」を丁寧にお聞きし、姿勢や筋肉のバランス、骨格の歪みなどを触診と動作検査でチェックしていきます。とくに肩甲骨や骨盤の動き、胸椎〜腰椎の連動性など、他院では見落とされやすい部分まで丁寧に評価します。
日常の中でできる簡単なチェックとしては、
-
背中を左右にねじったときの可動域
-
肩甲骨を寄せる・離すときの痛みの有無
-
深呼吸で背中にツッパリ感があるかどうか
などを確認してみてください。
気になる症状がある方は、無理に我慢せず、専門的な評価を受けることをおすすめします。

考えられる原因と医学的背景
背中の痛み・だるさ・倦怠感、その“裏側”にあるかもしれないこと
「背中が痛いだけなのに、なんでこんなに疲れるんだろう…」
そう思ったことはありませんか?実は、背中の痛みやだるさ・倦怠感には、筋肉や骨格の問題だけでなく、さまざまな医学的背景が関係していることがあると言われています。
たとえば、長時間のデスクワークやスマホ使用で、前かがみの姿勢が続くと、肩甲骨や背骨まわりの筋肉が常に引っ張られる状態になります。これがいわゆる“姿勢性筋疲労”で、血流が悪くなり、だるさや張り感を引き起こす要因のひとつとされています。
また、自律神経の乱れも見逃せません。特に、交感神経が優位になっていると、常に緊張状態が続き、筋肉がうまく緩まず、慢性的な倦怠感として現れることもあるようです。「リラックスしているつもりでも疲れが抜けない」という方は、このパターンに当てはまる可能性があります。
さらに、背中の特定の部位に痛みがある場合、内臓の関連痛の可能性もあります。たとえば、
-
右側の背中:肝臓や胆のう
-
左側の背中:胃や膵臓
-
背中の真ん中:腎臓や十二指腸
といったように、内臓が不調を起こすと、背中に痛みを飛ばすことがあるとされています。
当院では、こうした多角的な視点で原因を探るために、まず「姿勢評価」や「関節の動き」「筋肉の柔軟性」「呼吸パターン」などを丁寧にチェックしています。とくに骨盤・胸椎・肩甲骨の連動性が乱れている方が多く、それが結果的に背中の広範囲な負担につながるケースも見られます。
痛みの背景には、いくつかの原因が同時に存在することが多いため、「これだ」と決めつけず、全体のバランスを見ながら調整していくことが大切です。痛みが慢性化する前に、早めのケアと見直しをおすすめします。

当院の考え方と施術アプローチ
痛みの“背景”に目を向けた丁寧なアプローチ
「ただマッサージをしても、その場しのぎに感じて…」
そんなふうに話される患者さま、実は多いです。にっこり鍼灸整骨院では、背中の痛み・だるさ・倦怠感といった漠然とした不調に対して、根本原因を探ることを重視しています。
初回来院時には、まず丁寧な問診からスタートします。お仕事や生活習慣、睡眠の質、ストレスの有無などをお伺いしながら、体のどこに負担がかかっているのかを探っていきます。「え?そんなことが関係してるんですか?」と驚かれることもよくありますが、実はこの“聞き取り”がとても大事なんです。
次に行うのが、独自の検査です。姿勢のチェックはもちろん、肩甲骨・胸椎・骨盤の動き、呼吸に合わせた肋骨の広がりまで細かく見ていきます。特に背中に不調がある方は、骨盤と胸椎の動きにズレがあるケースが多く、それが筋肉の緊張や血流の滞りにつながっていると考えられています。
施術では、ただ押すだけの刺激的な手技は行いません。当院では、
-
骨格のバランスを整える「ソフト矯正」
-
筋膜の滑走性を改善する「筋膜リリース」
-
筋肉を深部から緩める「鍼灸アプローチ」
-
動かしながら整える「モビライゼーション」
など、症状や状態に合わせて組み合わせた施術を提供しています。
また、「動かすのが苦手」「トレーニングが続かない」という方には、寝ながら筋肉を刺激できるEMS機器を活用することもあります。これにより、無理なくインナーマッスルをサポートし、再発しづらい体づくりを目指します。
ご自身でも継続できるよう、自宅での簡単なストレッチやセルフリリースの方法もご案内しています。痛みやだるさは、体からのサイン。無視せず丁寧に向き合うことで、心も体もラクになるお手伝いができたらと考えています。

自宅でできるセルフケア&予防法
背中の痛み・だるさ・倦怠感に負けない日常の工夫とは?
「忙しくて整骨院に行けない…でも、何かできることはありますか?」
そんな声をよくいただきます。実は、日々のちょっとした工夫やケアの積み重ねが、背中の痛みやだるさ・倦怠感の予防にはとても重要だと言われています。
まず大切なのが、姿勢の見直し。
パソコンやスマホを使う時間が長いと、どうしても猫背になりがちです。骨盤が寝てしまった状態で長時間座っていると、胸椎や肩甲骨まわりの筋肉が引っ張られ、血流が悪くなりやすいとされています。クッションを使って骨盤を少し立てる、30分に一度は姿勢を変えるなど、ちょっとした意識が背中を守るポイントになります。
そして、当院でもおすすめしているのが「簡単ストレッチ」。
たとえば、座ったままできる肩甲骨まわしや、タオルを使った胸の開き運動は、無理なく続けやすく効果も期待できるとされています。ポイントは“頑張りすぎないこと”。「ちょっと伸びたな」「気持ちいいな」と感じる範囲で毎日少しずつ行うことがコツです。
また、意外と忘れがちなのが呼吸です。
浅い呼吸が続くと、自律神経が乱れやすくなり、倦怠感が出ることがあるとも言われています。深呼吸をするときは、お腹と背中がふわっと広がるのを意識しながらゆっくり吸って吐く。これだけでも、体の緊張がゆるみやすくなることがあるようです。
さらに、湯船につかる時間を大切にするのもおすすめ。温熱で筋肉がゆるむと、血流が改善され、疲れも取れやすくなると考えられています。お気に入りの入浴剤を使えば、気分転換にもなって一石二鳥です。
にっこり鍼灸整骨院では、患者さまの生活習慣に合わせたセルフケアの提案も行っています。「何から始めればいいか分からない…」そんな方でも大丈夫。あなたの生活スタイルに合わせた無理のないアドバイスをご案内いたします。
#背中のだるさの原因
#姿勢と筋膜の関係
#自律神経と倦怠感
#内臓と背中のつながり
#整骨院でできること