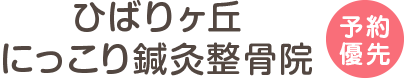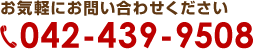六十肩がつらい…動かさないと悪化するって本当?当院が教える対策と施術法
2025年06月11日

六十肩に悩んでいませんか?肩が上がらない・夜間の痛みなど、放置は悪化のもと。当院独自の検査法と施術、セルフケア法を詳しく解説します。

六十肩とは?|加齢による肩関節の炎症と可動域制限
四十肩・五十肩との違いはあるの?
「最近、肩が上がらなくて…これって六十肩ですかね?」
そんなご相談、当院でもよく耳にします。実は“六十肩”という言葉は正式な医学用語ではなく、加齢にともなう肩関節のトラブル全般を指す俗称です。似た表現に“四十肩”や“五十肩”もありますが、年齢による呼び分けで、症状や原因はほとんど同じだと考えられています。
六十肩の正体は「肩関節周囲炎」
六十肩の正体は、「肩関節周囲炎」と言われています。これは、肩関節まわりの筋肉や腱、関節包などに炎症が起きることで、痛みや動かしづらさが生じる状態です。特に60代に多い理由としては、長年の使い方による摩耗や血流の低下、筋力の低下などが挙げられているようです。
「急に痛くなった」「何かを取ろうとした瞬間に肩がズキンとした」といった急性期の痛みから、「肩を上げるとつっぱる」「腕を後ろに回せない」といった可動域の制限へと移行するケースも多く見られます。
放っておくと“凍結肩”に?
六十肩は、痛みを避けて肩を動かさない状態が続くと、「凍結肩(フローズンショルダー)」と呼ばれる、さらに動きが悪くなる状態に進行すると言われています。つまり、我慢して放っておくことが、症状の長期化や悪化につながる可能性もあるのです。
にっこり鍼灸整骨院の見立て
当院では、肩だけでなく全身のバランスを確認しながら六十肩の状態を判断していきます。姿勢や筋膜の状態、骨盤のゆがみ、自律神経の乱れまで丁寧に検査することで、ただ痛みのある部位だけにとらわれず、根本的な原因にアプローチすることを重視しています。
また、施術では筋膜リリースや鍼灸、EMSによる筋力サポート、骨格調整などを組み合わせながら、「安全に動かせる範囲」を広げていくことを意識しています。
「もう年だから仕方ない」とあきらめず、まずは一度、ご自身の肩の状態をチェックしてみませんか?

六十肩のよくある症状と放置リスク
「腕が上がらない」「背中に手が回らない」ってよくあるの?
「最近、上着を着ようとしただけで肩がズキッとするんです…」
こうした声、当院でも本当によく耳にします。六十肩の症状は、肩関節まわりの炎症や癒着が影響して起こると言われており、特に腕を上げる・後ろに回すといった動きに制限が出やすいのが特徴です。
たとえば、洗濯物を干すときや髪を結ぶ動作、背中をかく動作など、日常生活の中で支障を感じる場面は意外と多いものです。痛みだけでなく「動かしづらさ」もセットで起こることが多いため、放っておくと不便さがどんどん増してしまう可能性があります。
夜間痛で眠れない人も
「夜、寝返りをうつたびに肩が痛くて目が覚める…」そんなつらい症状も、六十肩によく見られると言われています。これは、肩まわりの血流や炎症反応、筋肉の緊張などが関係しているとされ、安静にしていても痛むのが特徴です。
睡眠の質が落ちることで体の回復力も下がり、結果として症状の長期化につながるケースも少なくないようです。
放置してしまうとどうなるの?
六十肩は、何もしなくても自然とよくなるケースもあると言われていますが、実際には「肩をかばって動かさない期間」が長くなるほど、可動域が狭まってしまうことがあります。
特に気をつけたいのが“拘縮期”と呼ばれる時期。この段階では、肩関節の周囲組織が固まりはじめ、「凍結肩(フローズンショルダー)」と呼ばれる状態に進行するリスクもあるそうです。
にっこり鍼灸整骨院での見立てと施術
当院では、「肩が痛い=肩が悪い」とは限らないと考えています。姿勢や筋膜のねじれ、骨盤の傾き、日常の使い方など、複数の視点から原因を検査・触診し、施術方針を決めています。
たとえば、鍼灸で炎症を抑えたり、筋膜リリースで動きを改善したり、EMSで動かせない筋肉を刺激したりと、その方の状態に応じた施術を提案しています。
「動かさないと悪くなる」と頭ではわかっていても、痛みがあるとつい避けがちですよね。まずは今の状態を知ることから、一緒にはじめてみましょう。

当院の六十肩に対する考え方と検査法
痛みのある肩だけを診るわけではありません
「六十肩って、肩が悪くなる症状ですよね?」
よくそう聞かれますが、当院では「肩だけが原因とは限らない」と考えています。実は、姿勢のクセや筋膜のねじれ、骨盤の傾き、日常の動作のパターンなど、肩の動きに影響する要因は全身に広がっていると言われています。
肩の痛みや可動域の制限を根本から改善するためには、表面的な動きだけでなく、その背後にある体全体のバランスを見ることがとても大切なんです。
独自の姿勢評価と動作チェックで原因を探る
当院ではまず、姿勢の写真撮影や骨盤の傾きチェック、筋膜の緊張具合、左右差の観察などを行い、肩にどんな負担がかかっているのかを調べていきます。
「前から見たら肩が下がっている」「後ろから見ると肩甲骨の位置が違う」「背骨のカーブが崩れている」など、見た目のズレや動きのパターンからも重要なヒントが得られることがあるんです。
また、肩を動かすときに他の部位(たとえば腰や首)に力が入っていないかなども確認しながら、全体のつながりを意識して検査を進めていきます。
必要に応じて筋力チェックやEMS体験も
肩の痛みで動かせない期間が長引くと、筋肉が弱ってしまう場合もあると言われています。とくに三角筋や棘上筋といった肩の安定性に関わる筋肉は、知らないうちに機能が落ちているケースも。
当院では、筋力の評価を行いながら、必要に応じてEMS(電気的筋肉刺激)を使って筋肉の働きを助けるトレーニングも行っています。寝たまま受けられるので、運動が苦手な方でも無理なく始められる点もポイントです。
「自律神経の乱れ」に着目することも
六十肩の方の中には、肩こりや不眠、胃腸の不調など、肩とは関係なさそうな悩みを併発しているケースもあります。こうした状態は、自律神経のバランスが崩れている可能性があるとされており、当院では東洋医学的な視点も取り入れながら施術方針を立てています。
鍼灸や手技で体全体の緊張をゆるめ、自律神経の働きを整えることで、肩の動きにも良い変化が現れることがあるようです。
まずは、あなたの体の“本当のクセ”を知ることから始めてみませんか?

当院で行う六十肩への施術アプローチ
段階に応じた施術で「今できること」から始める
「痛いけど、無理して動かしてもいいんですか?」
六十肩の方から、よくいただく質問のひとつです。当院では、痛みの時期や肩の状態に合わせて“今の体に合った施術”を提案するようにしています。
炎症が強い急性期であれば、まずは筋膜のリリースや鍼灸などで痛みをやわらげることを目的に進めていきます。無理に動かすよりも、「どうすれば筋肉や関節に余計な力をかけずに済むか」に着目しながら対応します。
筋膜リリースと関節モビライゼーション
肩が固まりはじめている方には、筋膜リリースや関節モビライゼーションといった手技を行い、滑らかに動かせるように導いていきます。
「肩が動きにくいのは、関節の問題だけじゃない」とも言われており、筋膜のねじれや張り、肩甲骨まわりの可動性が影響しているケースも多く見られます。
EMSで“動かせない筋肉”をサポート
「動かしたくても動かせない」状態が続くと、肩を支える筋肉の働きが落ちてしまうことがあります。当院では、そういった筋肉に刺激を与える目的で、EMS(電気的筋肉刺激)も活用しています。
寝たままリラックスしながら行えるため、運動が苦手な方や痛みが強い方でも始めやすく、特にインナーマッスルの機能回復に適しているとされています。
鍼灸による炎症と血流へのアプローチ
鍼灸施術では、肩関節まわりのツボを刺激することで、筋肉の緊張をゆるめたり、血流の改善を図ったりします。血行不良や神経の興奮が関与しているケースでは、鍼灸が痛みの緩和に有効とされることもあるようです。
また、体全体の巡りや自律神経のバランスを整えることで、睡眠や精神的なストレスにも間接的に働きかける可能性があると考えられています。
再発予防のセルフケアも一緒にサポート
施術だけでなく、セルフケアの方法もしっかりお伝えしています。たとえば、肩甲骨の動きを良くする簡単な体操や、寝る前にできるリラックスストレッチなど、日常に取り入れやすいものから始められます。
「痛くなったら来る」ではなく、「再発しにくい体をつくる」ためのサポートまで、一緒に考えていきましょう。

ご自宅でできるセルフケアと再発予防法
まずは“痛みを悪化させないこと”からスタート
「六十肩、家で何をしたらいいんでしょうか…」
こんなご相談、当院でもよくあります。セルフケアはとても大切ですが、痛みの時期に合っていない内容をしてしまうと、かえって悪化につながることもあると言われています。
たとえば、痛みが強い急性期には無理にストレッチをするのではなく、冷却や安静を意識したほうがよいケースもあるようです。まずは“これ以上悪くしない”ことを意識してみてください。
回復期にはストレッチや軽めのトレーニングを
少しずつ痛みがやわらいできたら、関節の動きを取り戻すための簡単なストレッチや、肩を支える筋肉のトレーニングを取り入れていきます。
たとえば、壁に手をついてゆっくり腕を上げていく「ウォールウォーク」や、ペットボトルを使った軽いダンベル体操などが、筋肉の再教育に効果的だとされています。無理のない範囲で、少しずつ動かすことがポイントです。
肩甲骨まわりの動きも意識して
肩だけを動かすのではなく、肩甲骨の動きにも注目してみましょう。肩甲骨が固まっていると、肩の動きが制限されやすいと言われており、結果的に負担が集中することもあります。
当院では、「肩甲骨はがし」や「バンザイ体操」など、ご自宅でできる簡単なエクササイズもお伝えしています。イスに座ったままできるものも多いため、日常のスキマ時間で続けやすいですよ。
日常生活で気をつけたい動作習慣
無意識のうちに肩に負担をかけてしまう動作も、意外と多いものです。たとえば、重たい荷物を片手で持つ、無理な体勢で洗濯物を干す、スマホをずっと同じ腕で持つなど…こうした“クセ”が積み重なると、肩の状態が悪化しやすくなると考えられています。
当院では、日常生活の中での「動かし方のコツ」や「負担をかけない姿勢」も一緒にお伝えするようにしています。
セルフケア×施術で“再発しにくい体”へ
セルフケアは、施術と組み合わせることでより効果的だとされています。当院では、施術で動きやすくなった体を、そのまま放置するのではなく、「動きを維持するためのセルフケア」を合わせて提案しています。
無理なく、気持ちよく、続けられることが何よりも大切です。一緒に、肩のトラブルを繰り返さない体づくりを目指していきましょう。
#六十肩のセルフケア
#痛み期の注意点
#回復期のエクササイズ
#肩甲骨の動き改善
#再発予防の習慣化
#六十肩の施術方法
#筋膜と関節の調整
#EMSによる筋肉活性
#鍼灸で血流改善
#セルフケアの習慣化
#六十肩の検査法
#姿勢と筋膜チェック
#全身バランスの評価
#EMSで筋肉サポート
#自律神経と肩の関係
#六十肩の症状
#肩が上がらない
#夜間痛の悩み
#拘縮期リスク
#にっこり鍼灸整骨院の施術
#六十肩とは
#肩関節周囲炎の正体
#凍結肩に注意
#姿勢と筋膜の検査
#にっこり鍼灸整骨院の視点
#西東京市#ひばりヶ丘#東久留米市#新座市