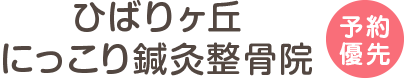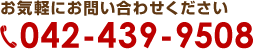「50肩・五十肩に効くツボとは?痛みを和らげるセルフケアと施術法を解説」
2025年05月28日

50肩・五十肩に効くツボを専門家が解説。痛みを和らげるセルフケア法や、ひばりが丘にっこり鍼灸整骨院での検査・施術方法も紹介します。つらい肩の痛みにお悩みの方はぜひご覧ください。

【50肩・五十肩とは?】症状の特徴とよくある誤解
そもそも「五十肩」ってどんな状態?
「最近、腕が上がらなくて、着替えるのが大変なんです…」
当院に来られる方から、こんな相談をよく受けます。それ、いわゆる「五十肩」かもしれません。
正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれるこの症状は、40代~60代に多く見られ、関節を構成する筋肉や腱、関節包に炎症が起きている状態だと考えられています。「40肩」「50肩」と年齢で表現されがちですが、実際には年齢に関係なく発症することもあると言われています。
特徴的なのは、突然肩に痛みが走ったり、腕を上げられなくなる、夜中にズキズキして眠れない…といった訴えがあること。特に、上着を着るときや髪を結ぶ動作で痛みを感じる方が多いようです。
五十肩にまつわる「よくある誤解」
「放っておけばそのうち改善するんでしょ?」という声もありますが、これは誤解されがちです。確かに、数ヶ月~1年ほどで自然に落ち着くケースもあると言われています。ただし、その間に肩周囲の筋力が落ちたり、関節が固まってしまい、結果として動かしづらいまま長期化するリスクもあるようです。
当院では、このようなケースに対して**「肩だけでなく、骨盤や背骨のゆがみもチェックする」**という独自の視点で対応しています。なぜなら、姿勢の崩れや筋膜の緊張が肩関節の可動域を狭めている場合も多いからです。
初回の検査では、肩の動きだけでなく、骨盤の傾きや背中の丸み、腕の筋肉の硬さなども含めて、全体のバランスを確認しています。そのうえで、鍼灸や骨格矯正、EMSを組み合わせた施術プランをご提案しています。
「肩が痛いのに、骨盤を見るんですか?」と驚かれることもありますが、全体のつながりを意識したケアをすることで、結果的にスムーズな改善を目指しやすくなると考えています。
#五十肩の症状
#肩が上がらない
#肩の痛みと骨格の関係
#にっこり鍼灸整骨院のアプローチ
#自然な回復をサポート
【東洋医学の視点】五十肩に効くとされる代表的なツボとは?
五十肩に使われるツボ、どこを押せばいいの?
「ツボって、本当に肩の痛みに効くんですか?」
こういった質問、当院でもよくいただきます。確かに「押すだけで楽になるなら試してみたい」と思いますよね。東洋医学では、気の巡りや血流を整える“経絡”という考え方があり、その流れにあるポイントが「ツボ」と呼ばれています。
特に五十肩に対して使われるツボには、肩井(けんせい)、肩髃(けんぐう)、曲池(きょくち)などが挙げられることが多いです。これらのツボは、肩の周囲の筋緊張をやわらげたり、関節の動きをスムーズにしたりといった目的で活用されることがあるようです。
ツボ押しは“肩だけ”じゃないのがポイント
「え?肩が痛いのに、肘の近くも押すんですか?」
そうなんです。東洋医学では、肩に限らず腕や背中など、関連するツボも組み合わせて使うことが多いです。たとえば、合谷(ごうこく)という手の甲のツボは、肩の痛みにも働きかけるとされています。全体の流れを整えることが大切だという考え方が背景にあるからです。
当院でも、鍼灸施術を行う際は、局所の痛みだけを見ずに、姿勢や筋膜のつながり、自律神経の状態までを丁寧に見ていきます。肩周囲の可動域だけでなく、背骨や骨盤の状態、そして血流の滞りもチェック。必要に応じてEMSでの筋肉活性や骨格調整を組み合わせて対応します。
また、セルフケアとしては、指で軽くツボを押しながら、深呼吸をしつつゆっくりと動かす方法がおすすめです。ただし、痛みが強いときは無理をせず、専門家に相談することが大切です。
「なんとなく肩が重いな」と感じたら、それは体からのサインかもしれません。気軽に取り入れられるツボ押しですが、正しく使うことで、毎日のケアとして役立てられることもあるといわれています。
#五十肩のツボ
#東洋医学と肩の痛み
#肩井肩髃曲池
#鍼灸と骨格矯正の併用
#セルフケアで肩を整える
【東洋医学の視点】五十肩に効くとされる代表的なツボとは?
ツボって本当に効くの?と思ったら読んでほしい話
「五十肩の痛みに“ツボ押し”って聞いたけど、実際どうなんだろう…」
そんなふうに思ったこと、ありませんか?実は東洋医学の世界では、古くから肩の痛みに対して「経絡(けいらく)」の流れを整えるツボ刺激が使われてきたといわれています。ツボとは、体をめぐる“気”や“血”が集まるポイントのことで、うまく刺激すると巡りが良くなり、筋肉の緊張や痛みの緩和が期待できると言われています。
当院でも、五十肩に悩む方に対して、鍼灸や手技を用いたツボへのアプローチを取り入れることがあります。ですが単なるツボ押しだけではなく、体全体のバランスや原因を探りながら施術を行っています。
五十肩でよく使われるツボたち
代表的なツボとしては、
-
肩井(けんせい)…首と肩の中間にあり、肩こりにもよく使われるツボ。
-
肩髃(けんぐう)…肩の外側、腕を横に上げたときにできるくぼみにあります。
-
曲池(きょくち)…肘を曲げたときにできるシワの外側の端。
-
合谷(ごうこく)…親指と人差し指の間にある、万能ツボといわれる部位。
これらのツボは、それぞれが「気の流れ」を整えるポイントとして知られています。特に肩井や肩髃は、直接的に肩の筋肉へ働きかけるツボとしてよく紹介されますが、東洋医学的には、離れた場所のツボ(例:手や肘)も合わせて使うことが全身の調和を図るために重要だとされているんです。
当院の施術では、ツボへの鍼灸施術に加え、筋膜の連動や骨盤・背骨の歪みの調整も行います。これは、「肩の痛みは結果にすぎず、原因はもっと別の場所にあることが多い」という考え方に基づいています。
セルフケアとしては、お風呂上がりなど血流がよくなったタイミングで、優しくツボを押してみるのもおすすめです。ただし、強く押しすぎたり、痛みがあるときは避けた方がよいとされています。
#五十肩とツボ
#肩井肩髃の場所
#東洋医学の視点
#鍼灸と骨格の連動
#にっこり鍼灸整骨院のアプローチ

【当院の検査と施術法】鍼灸+骨格調整で根本改善を目指す
五十肩の改善には“肩だけ”を見ていてはダメ?
「肩が痛いのに、骨盤や背骨まで診るんですか?」
初めて来院された方から、よくそんな驚きの声をいただきます。でも実はそれ、当院の考え方にとってはごく自然なことなんです。
五十肩と聞くと、多くの方が「肩の炎症だから、肩を治せばOK」と思われがちですが、私たちはそうは考えていません。肩の関節や筋肉がスムーズに動くためには、背骨や骨盤、さらには下肢とのバランスもとても重要だとされているからです。
そのため当院では、まずは全身の姿勢や関節の動きをチェックするところから始めます。具体的には、立ち姿勢・座り姿勢・肩の可動域の確認、さらに触診による筋緊張の状態を把握します。
鍼灸×骨格矯正×EMSの組み合わせでアプローチ
検査の結果を踏まえ、必要に応じて当院では以下のような組み合わせ施術を行っています。
-
鍼灸:肩関節まわりのツボやトリガーポイントにアプローチして、痛みの軽減や血流改善を目指します。
-
骨格矯正:骨盤や背骨のゆがみを調整することで、肩にかかる負担を根本から減らしていきます。
-
EMS:痛みで運動がしづらい方には、筋肉を寝たまま動かせるEMSを使い、インナーマッスルの活性を図ります。
これらはすべて、「その場しのぎ」ではなく、自然な形で肩の動きとバランスを取り戻すためのアプローチです。
また、施術後にはご自宅でも続けられるストレッチやセルフケア法をお伝えしています。例えば、軽めのツボ押しや、姿勢を意識した簡単な体操など。これにより、再発予防にもつながるように配慮しています。
五十肩というと、我慢しながら過ごしている方が多い印象がありますが、体はちゃんと変化に気づいてくれます。まずは小さな違和感でも、「今どこに負担がかかっているのか」を一緒に見つけていきましょう。
#五十肩の施術法
#鍼灸と骨格矯正の併用
#ひばりが丘にっこり鍼灸整骨院
#EMSで肩を動かす
#根本改善を目指す施術
【自宅でできるケア】五十肩におすすめのツボ押し&ストレッチ
無理せず続けられる、自宅でのケアって?
「病院に行くほどじゃないけど、なんとなく肩が重い…」
「施術を受けた後、家でできることってありますか?」
このようなお声をよく耳にします。五十肩は、急に激しい痛みが出たり、逆に何となく動かしづらさだけが残るケースもありますよね。そんなときにおすすめなのが、自宅でできる“ツボ押し”と“ストレッチ”の組み合わせ。
ただし、注意点もあります。どちらも“やりすぎない”ことが大切。少しずつ肩の可動域を取り戻していくイメージで行うのがコツです。
ツボ押しとストレッチ、それぞれのやり方とポイント
五十肩のセルフケアでよく使われるツボには、以下のようなものがあります。
-
肩井(けんせい):首と肩の中間地点。中指でじんわりと押すのがポイントです。
-
肩髃(けんぐう):腕を横に開いたときにできる肩のくぼみ部分。呼吸に合わせて優しく押すのがコツ。
-
曲池(きょくち):肘を曲げたときにできるシワの外側。肩とつながる経絡上にあるとされています。
押すときは、息を吐きながら10秒ほどかけて、ゆっくり圧を加えるようにします。グリグリと強く押す必要はなく、“心地よい刺激”を意識してみてください。
さらに、当院でも推奨しているのが腕を横に伸ばして胸を開くストレッチや、クロスアームストレッチ(片腕をもう一方の腕で抱え込むようにする動き)です。どちらも20秒ほど無理のない範囲で行うようにしましょう。
これらのセルフケアは、筋肉や関節の動きを促しながら、血流やリンパの流れを整えるサポートになるといわれています。日々のちょっとした積み重ねが、肩のスムーズな動きに近づく一歩になるかもしれません。
もちろん、痛みが強いときや動かすのが不安な場合は、まずは無理せず当院にご相談ください。当院では姿勢や骨格の状態、筋膜の硬さも含めて検査し、根本原因を見極めたうえで施術とセルフケア指導を行っています。
#五十肩セルフケア
#ツボ押しとストレッチ
#肩井肩髃曲池
#自宅でできる肩ケア
#にっこり鍼灸整骨院のアドバイス
#西東京市#ひばりヶ丘#東久留米市#新座市